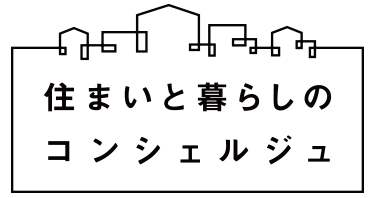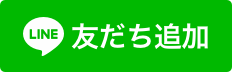| 本稿の概要 |
|---|
| ・借地権は相続できる。相続する際、地主の許可は不要。借地権の登記がされているときは名義変更が必要。 ・借地権には複数の種類があり、契約内容や相続税の計算方法に違いがあるため、確認が必要。 ・法的義務はないものの、相続は地主に連絡しておくほうがよい。売却・増築・改築は承諾がいる。 |
借地権を相続する際、「今の契約のまま相続できる?」「名義変更が要る?それとも、地主さんと契約し直すの?」と悩む方が少なくありません。あなたも、不安を感じていないでしょうか?
ご安心ください。借地権の相続は、全体像が分かればそれほど難しくありません。複雑なところは専門家に任せ、将来的なトラブルの回避に注意を払えば、安心して相続を進められますよ。
本稿では、借地権の相続についての基礎知識をご紹介します。借地権の相続や名義変更で悩んでいる方のご不安を解消しますので、ぜひ最後までチェックしてください。
借地権・借地権付き建物の相続は可能か

まずは、結論からお伝えしましょう。借地権の相続には、以下のような特徴があります。
- 借地権には複数の種類がある
- 借地権は相続できる
- 借地権の相続に地主の許可は不要
- 借地権の登記がされているときは名義変更が必要
借地権相続の特徴を端的にお伝えすると、上述のようになります。しかし、どれも少し補足説明が必要ですので、これから詳しく解説していきます。
借地権とは?
まずは、借地権の種類からご紹介します。
▼ 地上権と賃借権
借地権とは《建物の所有を目的とする地上権》または《土地の賃借権》のことです。これは「借地借家法 第2条」で定義されています。
参考:借地借家法 第2条
さっそく、2種類の借地権が登場しました。しかし、ほとんどの借地権は「賃借権」です。「地上権」による契約は、特殊なケースに限られます。
ですから、ここからは賃借権をベースに「借地権」の解説を進めます。
| 地上権 | 建物や竹木を所有する目的で他人の土地を使用する権利。たとえば、道路・鉄道・トンネルなどに使用する場合など。民法第265条《地上権の内容》に規定。 |
|---|---|
| 貸借権 | 賃貸借契約にもとづいて、他人の土地を賃料を支払って使用する権利。ほとんどの借地権はこちら。民法第601条《賃貸借》に規定する賃貸借契約にもとづく。 |
借地権の最大の特徴は、土地と建物の所有者が異なる点です。つまり、建物は借地権を持つ人が所有しますが、土地は地主のもの ―― ということです。
なお、借地権が設定されている土地のことを《底地 (そこち)》と呼びます。
▼ 旧借地権・普通借地権・定期借地権
借地権は、大別するとさらに3つに分けられます。ご紹介しましょう。
| 旧借地権 | 明け渡しを要求できる正当な理由がなければ、半永久的に更新し続けられる |
|---|---|
| 普通借地権 | 今の基本ルールで、更新は地主の事情を考慮しておこなわれる |
| 定期借地権 | 更新ができず、契約期間が満了すると土地を更地にして返還する必要がある |
1992年8月に施行された《借地借家法》によって、普通借地権と定期借地権が増えました。1992年7月31日以前に契約を締結した借地権は「旧借地権」と呼ばれています。
旧借地権は、非常に不利な立場に置かれがちだった賃借人を保護する目的で制定されました。しかし、賃借人の権利を強化したところ、今度は地主に不利な状況が多く発生しました。
その結果、土地を貸さない地主が増えてしまいました。そこで、地主と賃借人の権利のバランスを図るために設けられたのが「普通借地権」と「定期借地権」です。
借地権を相続する際は、どのようなタイプの借地権なのか確認することが重要です。
借地権・借地権付き建物は相続できる?
借地権および借地権付き建物は、相続の対象なのでしょうか?―― 結論から言うと、借地権は遺産として相続できます。
相続人は、借地権を相続することで地主との借地契約を引き継ぎ、引き続き土地を利用できます。借地権を相続すると、賃料の支払い義務も引き継がれます。
借地権の相続に地主の許可は必要?
法定相続人が借地権を相続する場合、地主の承諾や承諾料は原則として不要です。借地権は相続財産として相続人に引き継がれるため、被相続人が亡くなった際、自動的に相続人に継承されます。
契約書の名義の書き換えや、それにともなう名義変更料の支払いも、義務ではありません。ただし、地主との良好な関係を保つため、相続が発生したことを地主に連絡しておくことが推奨されます。
一方、地主の承諾が要るケースもあります。たとえば、以下のケースです。
- 遺贈(相続人以外の第三者に遺産を譲る)の場合
- 建物を売却したり転貸したりする場合
- 建物の増築や改築(建て替え)をする場合
貸借契約の借地で、上述のケースに当てはまる行為を無断で実行すると、契約解除の理由になり得ます。必ず地主に相談して、承諾を得てから実行しましょう。
借地権の名義変更とは?相続手続きの流れを解説
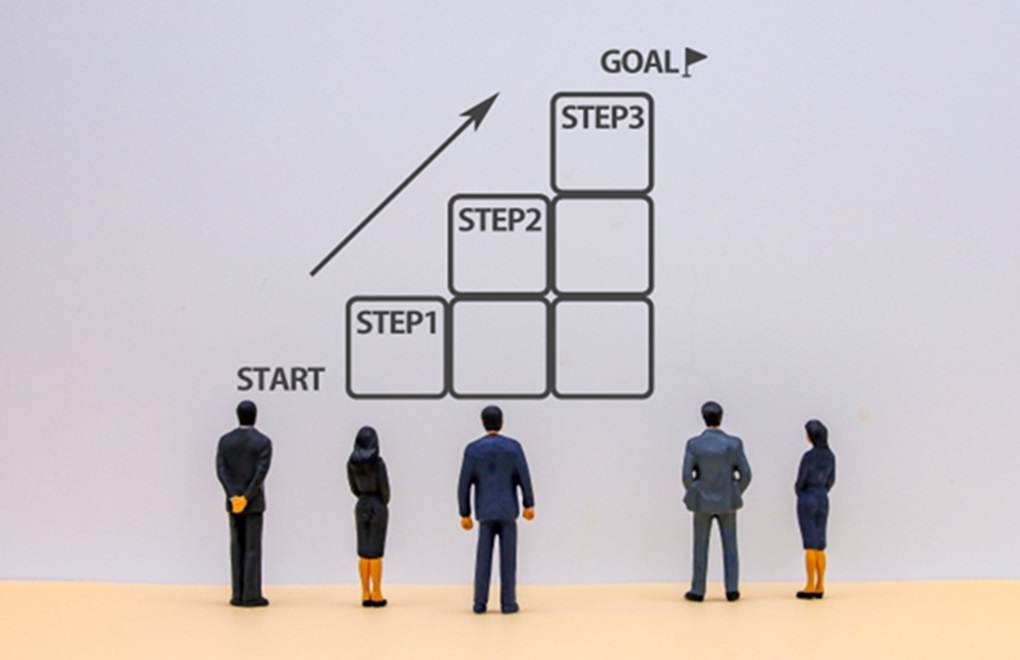
つづいて、借地権の名義変更と、相続手続きの流れをご紹介します。
借地を相続するご予定の方や相続が発生した方は、本章をご覧いただくと、スムーズに相続を進められますよ。
名義変更とは?重要性を解説
借地権の相続手続きにおける《名義変更》とは、相続人が《亡くなった方が持っていた権利》を正式に自分の名義に変更する手続きのことを指します。
具体的には《借地権》と《建物の所有権》が該当し、法務局で登記することで名義を変更できます。ただし、借地権は登記されていないケースが少なくありません (詳しくは後述)。
▼ 名義変更の重要性
2024年4月から相続登記が義務化されているため、相続登記が必要です。名義変更を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の期限は、相続の開始があったことを知り、かつその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。詳しくは、こちらの記事をご覧ください。
一方、借地権の登記は法律で義務付けられていません。そのため、登記されていないケースが少なくありません。
借地権の登記がない場合は、建物の名義変更のみで手続きが完了します。
▼ 借地権が登記されていない場合
では、被相続人が借地権を登記していなかった場合、相続人も登記しなくてよいのでしょうか?
繰り返しになりますが、借地権の登記は義務ではありません。また、借地上に借地権者名義で登記された建物がある場合は、それをもって借地権を第三者に主張できます。
参考:借地借家法 第10条
また、登記すると、以下のような想定外の事態が起こったときもスムーズに借地権を主張できます。
- 地主(土地の所有者)が変わった場合
- 地主が二重に土地を貸し出していた場合
- 建物が火事や災害などにより滅失してしまった場合
- 将来的に相続人が増えたり、次の相続が発生したりした場合
登記をおこなうことで、このような事態に起因するトラブルを未然に防ぎやすくなります。
なお、借地権の登記は地主の承諾や協力が欠かせません。しかし、借地権の登記は地主にはあまりメリットがないため、承諾が得られない場合もあります。
相続手続き(名義変更)の流れ
つづいて、相続手続きの手順をご紹介します。一般的に、借地権の相続は以下の流れで進んでいきます。
- 登記事項証明書の取得
- 遺産分割協議
- 書類の準備
- 地主への通知
- 相続登記
- 地代の支払い
順番に、補足説明をします。
▼ 登記事項証明書の取得
対象となる不動産の全部事項証明書を法務局で取得します。名義変更の対象となる不動産の詳細や、借地権の登記の有無を確認します。
▼ 遺産分割協議
だれが借地権を相続するかを話し合います。単独で相続するほうが、将来的なトラブルを回避しやすいでしょう(詳しくは後述)。
▼ 書類の準備
以下の書類が必要になります。遺産分割協議と同時に集めるとスムーズです。
- 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 被相続人の住民票の除票、または戸籍の附票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人の印鑑証明書
- 固定資産税評価証明書
- 遺産分割協議書または遺言書
なお、必要書類はケースバイケースで変わる場合があります。法務局や司法書士にご確認いただきながら、取得を進めてください。
▼ 地主への通知
相続が発生したことを地主に伝えます。法的には通知は必要ありませんが、良好な関係を維持するためにおこなうことが望ましいです。
▼ 相続登記
借地権と建物の所有権を相続人名義に変更するための登記手続きをおこないます。準備した書類を持参し、法務局で名義変更を申請します。
▼ 地代の支払い
相続人は、契約にもとづいて地代を支払います。
なお、上述の流れは状況によって順序が入れ替わる場合もあります。手続きが複雑になるケースもあるため、専門家に相談することをおすすめします。
東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」でも、司法書士や税理士などの専門家と連携しながら、アドバイスをさせていただくことが可能です。
ご不安な方は、お気軽にご相談ください。
借地権の相続に関する注意点・トラブル

最後に、借地権の相続に関する注意点やよくあるトラブルをご紹介します。本章を参考にしていただくと、借地権の相続をトラブルなく進めやすくなりますよ。
借地権契約の内容を確認しよう
借地権を相続する際、借地権の内容を確認することが重要です。借地権を適切に管理し、地主との関係を円滑に保つために、しっかりチェックしておきましょう。
確認すべき5つのポイントをご紹介します。
▼ 契約の種類
借地権には「旧借地権・普通借地権・定期借地権」の3種類があります。それぞれ契約内容や契約期間、更新条件が異なるため、どの種類の借地権が適用されているかを確認しましょう。
▼ 契約期間と更新条件
借地契約の契約期間(存続期間)や更新の条件を確認しましょう。旧借地権や普通借地権の場合は、契約更新が可能です。定期借地権の場合は、契約満了時に土地を返還する必要があります。
▼ 地代の支払い条件
地代の金額や支払い方法、値上げの条件について確認しましょう。地代の変更は地主との合意が必要であり、契約書に記載された内容が優先されます。条件を把握しておきましょう。
▼ 更新料や承諾料の規定
更新料や譲渡時に発生する承諾料について、定められている場合があります。これらの費用がどのように設定されているかを確認しておきましょう。
▼ 建物の取り扱い
借地権にもとづいて建てられた建物の取り扱いについても、確認が必要です。契約終了時に建物をどうするかについての条項(取り壊す?地主に買い取ってもらう?)があるかを確認しましょう。
税金に注意しよう(借地権の相続も相続税の対象)
借地権は財産として評価されるため、相続税の対象になります。適切な手続きをおこなわないと、予期しない税負担が発生する可能性があります。
借地権の相続税評価額は、契約の種類によって異なります。
計算式は国税庁等のWebサイトで公開されていますが、計算も難しく、もし借地権の評価額を誤って低く見積もってしまうと、税務署からの確認や追徴課税のリスクが高まるので、税理士等の専門家に相談することをおすすめします。
参考:国税庁「貸宅地の評価」
借地権を相続した場合、相続税の申告が必要です。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月以内です。
相続税は、相続財産の合計額から基礎控除額を引いた後に課税されます。ですから、借地権の評価額を正確に把握しておくことが重要です。
なお、借地権にも「小規模宅地等の特例」が適用される場合があります。相続税評価額が大幅に減額される制度ですので、条件を確認し、適用をご検討いただくとよいでしょう。
借地権を兄弟姉妹等で共有するとトラブルになりやすい
借地権を兄弟姉妹等で共有すると、権利関係が複雑化してトラブルになりやすいので、相続の際はご注意ください。
借地権を共有すると、借地権の利用や管理に関して、相続人全員の同意が必要になります。そうなると意思決定が難しくなり、意見の対立が生じやすくなる恐れがあります。
とりわけ地代や相続税の支払い、建物の改築や売却などの重要な決定では、合意形成が困難になるリスクが高まります。
他にも、以下のリスクもあるでしょう。
- 次の相続の複雑化
- 地主との関係の悪化
共有名義の借地権が次の世代に相続されると、さらに権利関係が複雑化します。相続人が増えることで、共有者間の意見の不一致が増え、トラブルがさらに深刻化する恐れがあります。
借地権の相続後、地主から地代の値上げや契約条件の変更を求められることもあるでしょう。共有名義の場合、全員が同意しなければならないため、交渉が難航するケースが多く見受けられます。
地主への返答に手間取ると、地主の心証を悪くする恐れもあります。これらの理由から、借地権を相続する際には、できる限り単独名義での相続が推奨されます。
借地権の相続で悩んだら、専門家に相談しよう
これまで解説してきたとおり、借地権の相続は比較的単純であるものの、トラブルが起こりやすい側面もあります。
また、相続手続きやトラブルの解決には専門的な知識が必要です。借地権の相続手続きに不安がある方は、以下のような専門家にご相談いただくと、安心して進められるでしょう。
| 弁護士 | 法律的な問題やトラブルが発生した場合、弁護士が適切。相続人同士のトラブルや地主との交渉が必要な場合、法律にもとづいたアドバイスや交渉をおこなってくれる。 |
|---|---|
| 税理士 | 借地権の相続には相続税が関わるため、税理士への相談も重要。相続税の評価額の計算や申告手続きについてのアドバイスを受けられる。 |
| 司法書士 | 借地権の名義変更や登記手続きに関しては、司法書士が専門。相続後の名義変更登記や必要書類の準備をサポートし、法務局への申請を代行してくれる。 |
| 不動産会社 | 借地権付きの不動産の売却や評価については、不動産会社が役立つ。また、地主との交渉や売却手続きに関しても、不動産の専門家の立場からアドバイスをくれる。 |
| 建築会社 | 借地に建物を建てる場合や改築を考えている場合は、建築会社への相談も必須。地主の承諾が必要な場合があるため、事前に建築会社と相談しておくことが重要。 |
「まずは、相談がしたい」と言う方は、私たちコンシェルジュへご相談ください。中立的な立場から、総合的なアドバイスをご提供させていただきます。
各専門家をご紹介することもできますので、連携しながらお客さまをサポートさせていただきます。
借地権の相続で悩んだら《住まいと暮らしのコンシェルジュ》へ
借地権は、相続できます。相続する際、地主の許可は必要ありません。借地権の名義変更の登記も、不要な場合が多いでしょう。比較的簡単に、相続できるのではないでしょうか?
ただし、借地権には複数の種類があり、契約内容を確認しておくことが重要です。法的義務はないものの、相続が発生したことを地主に連絡しておくことが推奨されます。
また、相続税の対象にもなります。トラブルが発生しやすい側面もありますので、手続きや問題回避にご不安がある方は、専門家にフォローしてもらいながら進めることをおすすめします。

「各専門家に連絡するのが面倒」「ワンストップで済ませたい」とお考えの方は、東急株式会社「住まいと暮らしのコンシェルジュ」にご相談ください。
私たちコンシェルジュが、各専門家と連携しながら、お客さまの状況に合ったご提案をさせていただきます。ぜひ店舗相談やオンライン相談、メール相談、フリーダイヤルをご利用ください。
定期的に借地権に関するセミナーも開催しております。詳しくは「イベント・セミナー」ページをご覧ください。